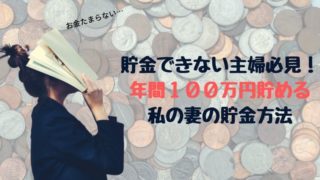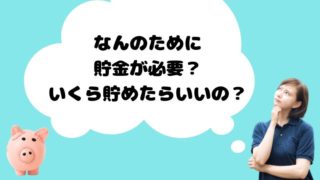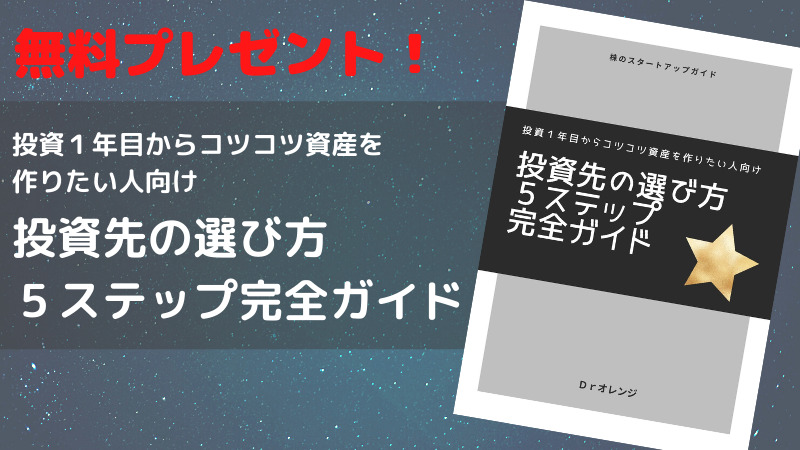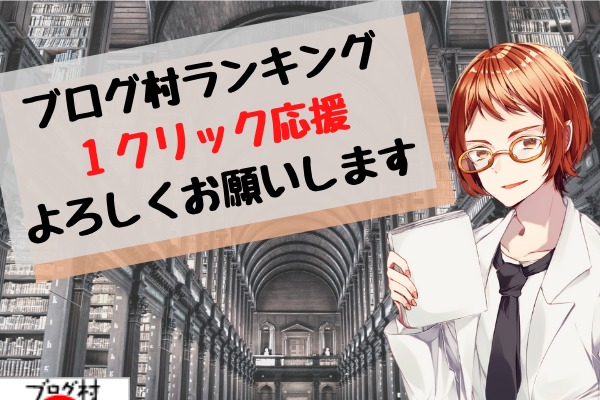今回は貯金ができない家庭にお悩みの方向け。私自身の経験や周りの友人の状況から、貯金できない家庭の3パターンをご紹介しつつ、それぞれの解決方法をお伝えします。
一応私はFPの資格をもっていて投資も8年ほどやっており、他人よりお金に詳しいので参考になるかと。
子供の学費やマイホーム購入、老後の生活費など将来お金に困らないようぜひこの記事を役立ててください。
貯金ができない家庭の3つのパターンと解決方法【FP保有者が分析】
そもそも貯金できない家庭ってどのくらいでしょうか。私の家庭は珍しいのかな?それともみんなのおうちも全然貯金してないのかな?なんて気になりますよね。
国が毎年調査してるので調べてみました。
| 世帯主年齢 | 金融資産を 保有していない |
資産100万円未満 |
| 20代 | 22.9% | 35.1% |
| 30代 | 15.8% | 11.3% |
| 40代 | 18.7% | 7.2% |
| 50代 | 21.8% | 5.7% |
| 60代 | 23.7% | 4.5% |
| 70歳以上 | 31.1% | 4.9% |
私は30代なので、約30%ちかくの家庭が100万円未満しか貯金していません。これから子供の学費や住宅ローンなどが待ち構えているのに100万円もないなんて結構ヤバいですよね…。
では私の周りでよくみる『貯金できない家庭3パターン』を見ていきましょう。
貯金できない家庭よくある3パターン
- お互い収入と支出が別々
- 固定費を見直ししてない
- お互いの浪費を黙認
貯金できない家庭のパターン1.お互い収入と支出が別々
夫婦がそれぞれの収入からお金を使っていて、家計がひとつになっていないパターンです。
特に共働きの夫婦に多い傾向があるようですね。ハッキリ言ってこの状態だと貯金は厳しいです。
なぜなら家庭の全体的な収入と支出が見えてこないので、どこを改善していいか見当がつかないからです。
それにお互いが「向こうが貯金してるだろ」と期待してまったく貯めていなかったり、逆に「わたしはこんなに節約してるのにムダ遣いばっかりしててずるい!」と夫婦ゲンカの原因にもなりかねません。
お互いの貯金も全て一緒にしろとまでは言いませんが、せめて毎月の収入・支出はオープンにしないといつまでたっても貯金できない家庭のままです。
まずは家計をひとつにして貯金のスタートラインに立ちましょう。
貯金できない家庭のパターン2.固定費を見直ししていない
2つ目のパターンは固定費の見直しをしていないことです。
固定費の見直しは節約に効果バツグン。
特に下記の3つは要チェックです。
- ケータイ代
➔格安スマホへ。 - 保険料
➔死亡保険、収入保険など最低限に。 - 定額課金サービス
➔アマゾンプライムやサプリメントの定期購入など
家庭によっては、固定費の見直しだけで月5万円くらい節約になる可能性もあります。
自分の中で当たり前になっているものが実はとってもムダだった…。なんてことはよくある話。パートナーと家計をひとつにしてお互いの支出を「見える化」すれば、節約のポイントがきっと分かってくるはずです。
本当に生活に必要なものなのかをよーく話し合って不要な固定費はどんどん削っていきましょう。
ちなみによく『家賃を見直しましょう!』というアドバイスを目にしますが、それはやりすぎかなと。
家賃って見直したところで引っ越し費用が数十万単位でかかりますし、それで月数万円トクしてもあまり意味ないですね。
現在家賃20万円のマンションに住んでる、とかいうなら話は別ですが、基本家賃の見直しは『ホントに家計が行き詰った時の最終手段』にしておくのがベターだと思います。
貯金できない家庭のパターン3.お互いの浪費を黙認している
最後は、お互いの浪費・ムダ遣いを黙認してしまってるパターン。自分が飲み代で3万円使った翌日、ショッピングで奥さんがちょっと高い洋服を買っても文句言えないですよね…。
自分の浪費をやめないとパートナーの浪費も黙認してしまいます。
まずは自分が、『一切ムダ遣いしてない!』と自信をもって言えるような生活を心がけるとともに、パートナーにそのことをよく伝えておくのが大切です。
そうすれば、『あの人が節約してるんだから私もガマンしよう』とお互いが自主的に節約できるようになり、結果貯金するゆとりが生まれてくるでしょう。
まとめ
今回は『貯金できない家庭の原因と解決方法』をテーマに私の周りでよくみる3パターンをご紹介しました。原因と解決方法をカンタンにまとめるとこんな感じ。
- 家計がバラバラ
➔ひとつにする - 固定費を見直してない
➔見直す - 浪費を黙認
➔自分にも厳しく
これらを徹底できれば貯金ができる家庭になれるはず。ぜひ実践してみてください。
しかし、自分たちではムズしそう…。という方向けに、次のページでプロに家計を見直してもらえる方法をご紹介します。
(次ページ)無料でプロにみてもらう方法



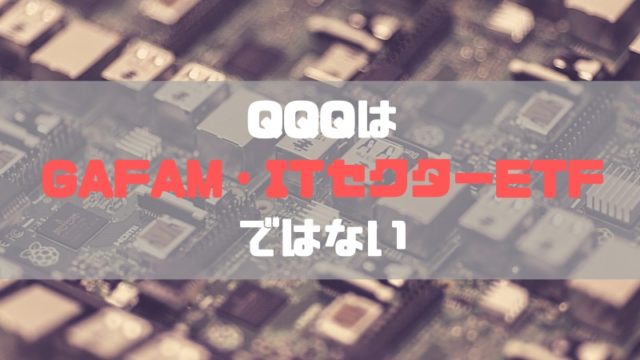
は儲かる?4つの儲け方をご紹介!.jpg)